「AI、気になるけどちょっと難しそう…」そんなモヤモヤに、手元から突破口を。
Webアプリや業務系システムには慣れてる。でもAIは…と二の足を踏むあなたにこそ。手を動かしながら理解を深める、“ゼロから”のAI本が出ました。
「AI、やってみたい」気持ちを動かす1冊
2025年7月12日、翔泳社から『ゼロから理解する AIプログラミング入門』が発売されます。タイトル通り、プログラミング経験はあるけどAIは初めて…という方向けの内容です。
要はこう、「図解とコードで、手を動かしながら学ぶ」構成。
AIといえば数式ゴリゴリのイメージがありますが、本書はあくまで“実装ベース”。難解な理論に振り回されることなく、Pythonのコードを写経しながら少しずつ“AIの地図”を描けるよう設計されています。
構成のポイントは「1章完結」「コード優先」「最後に画像認識」
この本、よくできてます。注目ポイントは3つ:
✅ 数式よりもコード重視。まず動かす。理屈はあとでついてくる。
✅ 1章1テーマ完結型。子どもが昼寝してる間でも進めやすい(実体験)。
✅ 最後に「画像認識」の物体検出まで体験できる。これ、実務に効きます。
40代で学び直すとなると、“ながら学習”や“すきま時間”が超大事。そんなリアルを考慮した構成です。
「PoCで使えるレベル感」がちょうどいい
物体検出って、物流・製造・小売りなど多くの業界でニーズ急増中。PoC(概念実証)段階なら、書籍レベルの知識とスキルでも十分通用することが多いんです。
つまり本書を完走 → GitHubにコードをアップ → 社内で共有 だけでも、
「あ、〇〇さんAIもいけるの?」
というリアクションが得られるはず。資格より“動くデモ”が信頼を得る世界だからこそ、コードで語る姿勢が響きます。
「技術ブリッジ役」としてのポジションづくり
社内でAIプロジェクトが始まりそう。でも、AI専門家と現場とのギャップが大きすぎて話が通じない──これ、ありがちな悩みです。
そんなとき「AIも分かるエンジニア」が1人いるだけで、橋渡しがスムーズになります。40代エンジニアの強みはまさにそこ。“業務ドメインを深く理解したうえで、AIの言語も話せる”存在。
まずはこの入門書で、小さな一歩を踏み出してみませんか?
まとめ
「動くコード」こそ、40代からのキャリアの説得力。
週末2時間だけでも、自分の手元でAIを動かす。その一歩が“社内外の味方”を呼び寄せる起点になります。
まずは写経してみよう。「分かる」は「動かす」とセットでやってくる。
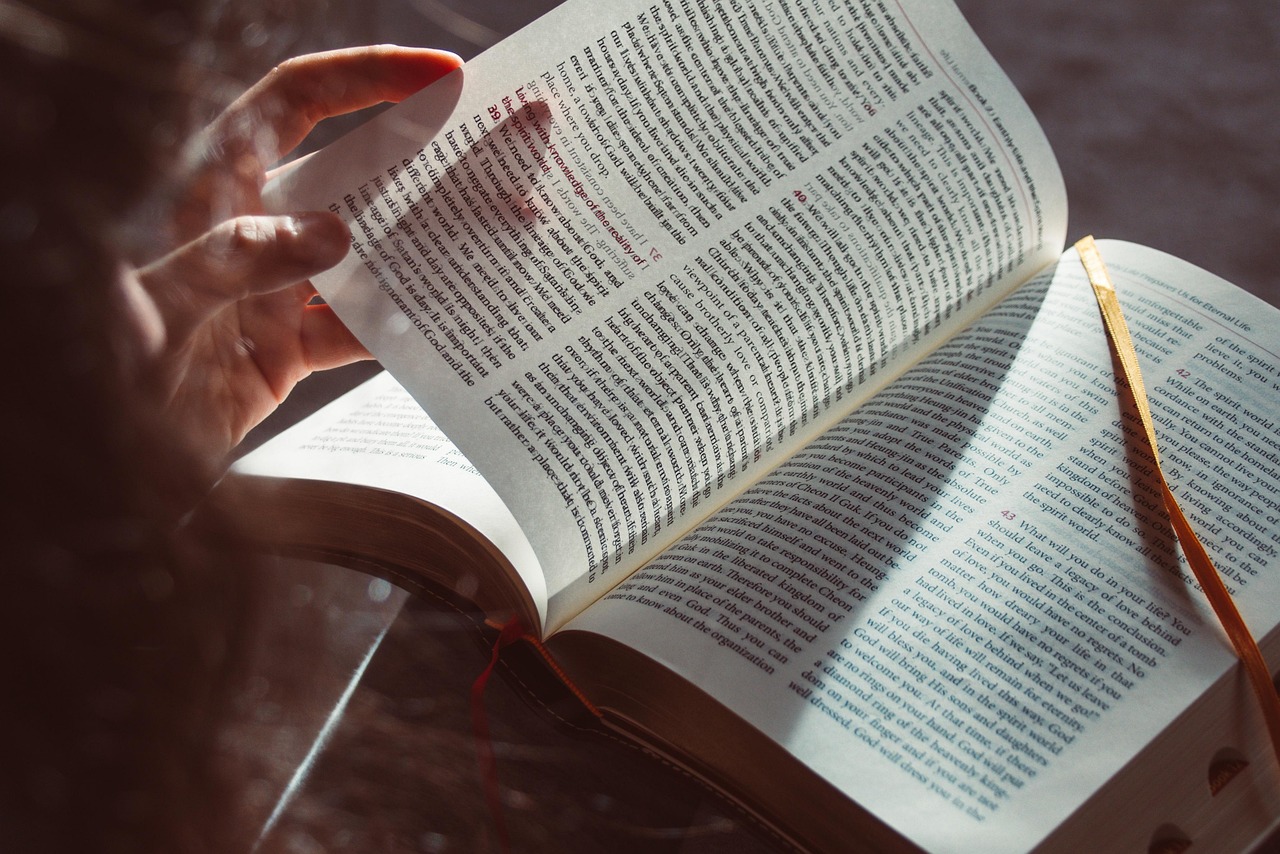

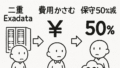
コメント