“Monday Blues”は気のせいではなかった──身体に「痕跡」が残っていたのだ。
月曜の朝、スマホのアラーム音にイラッとしながら、「まだ寝かせて…」と布団にしがみつく──月曜あるあるですよね。
「また1週間が始まるのか…」と頭が重くなるその感情、実は“気分”だけで済まされないとしたら?
カレンダーが体内時計を狂わせる──髪に刻まれた「月曜ストレス」の証拠
この衝撃的な事実を明らかにしたのは、香港大学の研究チーム。
彼らは英国で実施中の高齢者調査(ELSA)に参加する3,500人超を対象に、「曜日ごとの不安」と「毛髪中のコルチゾール(ストレスホルモン)」の関係を調査しました。
結果は驚きのひと言。
✅ 月曜に不安を感じる人の髪からは、他の曜日より23%も多くのコルチゾールが検出
✅ 働いていない高齢者でも、同様の傾向あり
つまり、「会社行きたくない…」という気持ちがなくても、“月曜という存在”が体にストレスを刻んでいるんです。
コルチゾールは、ストレス応答をつかさどるHPA軸の活動を示すマーカー。
これが慢性的に高い状態が続くと、
- 免疫力低下
- 血糖異常
- 動脈硬化の促進
といった“体に静かに効いてくる”不調の土壌をつくってしまいます。
「月曜に心筋梗塞が多い」は都市伝説じゃなかった
今回の研究は、2005年の有名なメタ解析──「心筋梗塞は月曜日に約19%多い」という統計──に対し、明確な生理的メカニズムを与えるものです。
コルチゾール過多の状態は、心血管イベントのリスクを高めます。
つまり、「月曜が嫌だ」は、気の持ちようではなく体が戦闘モードに入っているサインとも言えるのです。
育児に例えるなら、「イヤイヤ期の月曜」。
毎週訪れるイヤイヤに、体も心も振り回されている状態ですね。
ストレスは“予定表”から来ていた──あなたの体は社会に縛られている?
注目すべきは、今回のストレス反応が「就労有無に関係なかった」こと。
これはつまり、「会社が原因」ではないのです。
研究者はこう言います:
「社会文化的な“時間割”が、私たちの生理に組み込まれてしまっている」
たとえば、リモートワークや週休3日制に移行しても、月曜は“新しいサイクルの始まり”として、無意識下の緊張を誘発してしまう。
これが「カレンダー・ストレス」の怖いところです。
エンジニアの月曜対策は“タスクよりも自律神経”に目を向けよう
月曜ストレスが「思い込みではなくホルモン反応」だとしたら、対策も見直す必要があります。
✅ 朝イチからの会議を避け、スロースタートに切り替える
✅ 週末の夜更かしをやめて、「月曜の朝」に備える
✅ 日曜夜に「軽い運動」や「瞑想」を取り入れ、交感神経を整えておく
また、副業エンジニアにとっては、**「月曜はクライアント業務を入れない」**など、設計レベルでリズムを整える工夫も有効です。
ちなみにShoは「月曜の朝はコーヒーを淹れる→散歩→VS Codeを開く」までを“ルーチン”にしています。“月曜の自分”を「こっち側の世界」へ引き戻す習慣、大事ですよ。
「月曜が怖い」は身体のSOSだった
カレンダーがあなたの自律神経を支配している。
だからこそ、意識的な“月曜シフト設計”が必要だ。
まずは、「月曜の始まり方」を棚卸ししてみましょう。
週のリズムは、キャリアと健康の“屋台骨”です。
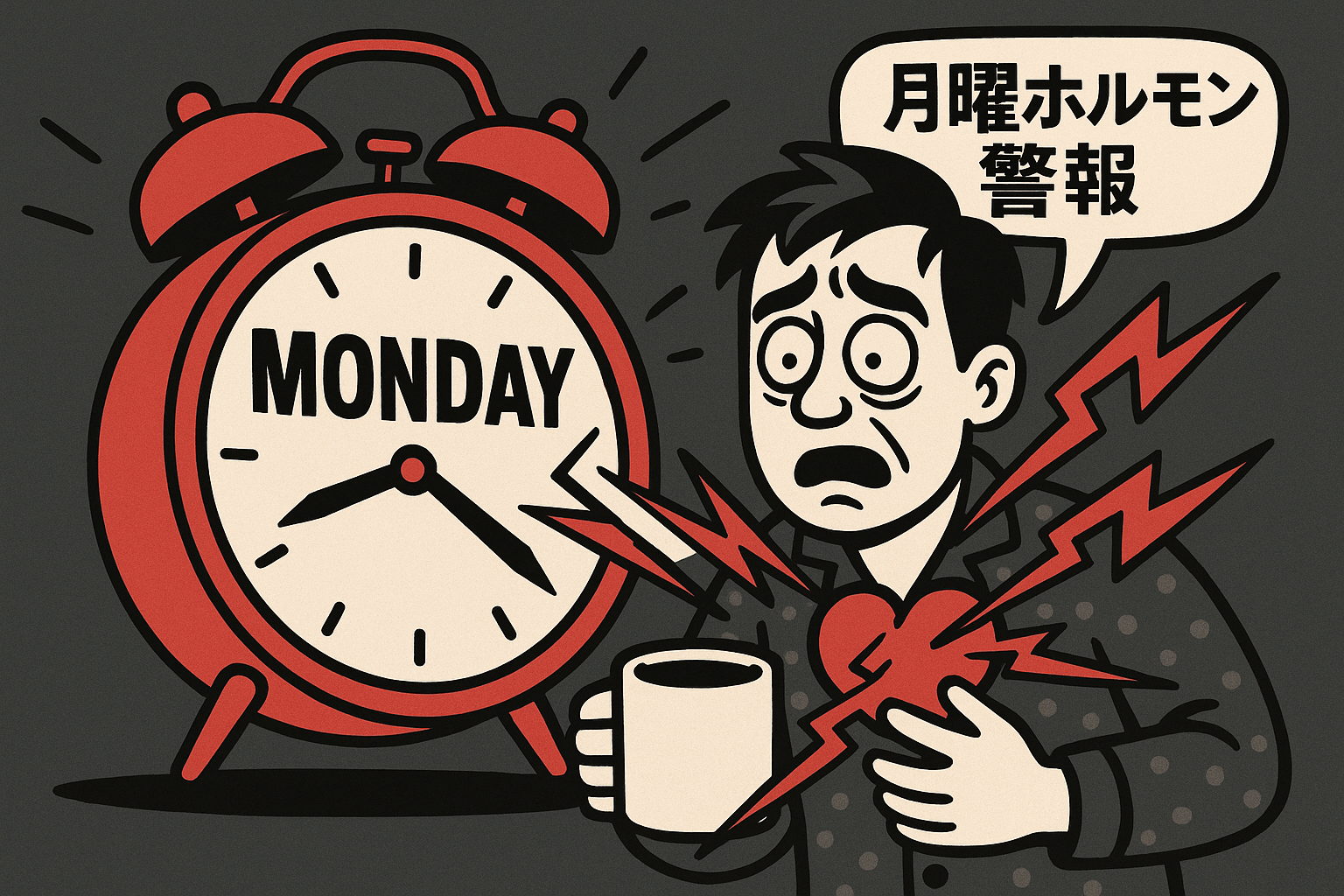


コメント