AI導入=生産性向上、は幻想だった?
2025年、日本の職場では「AIを導入したのに、なぜか忙しくなった」という声がじわじわと広がっている。Asanaの最新調査によると、ナレッジワーカーの情報検索にかける時間は週15時間で、なんと前年より9時間も増加。加えて、同僚との対応は週12時間(+7)、コラボツール使用も10時間(+4)に膨らんでいる。
このデータは、AIによる効率化が期待されたにもかかわらず、実際は業務の「上乗せ」になっているという逆説――つまり“AIパラドックス”の存在を浮き彫りにしている。

社内の問い合わせ対応をAIチャットボットに任せているのだが、精度の低さから社員が二度手間になり、結果的に自分の工数が増えてしまった。導入目的が「とりあえずAIを使ってみる」だったことが問題だろう
このように、AIが「部分的な便利ツール」としてしか扱われていない場合、その導入は単なる“業務の肥大化”に直結してしまう。特にプロセス全体の見直しや、目的の明確化なしにAIを導入すると、その場しのぎの対応に終始し、現場の混乱を招くのだ。
Asanaのレポートでは、AI導入を本格的にスケールできている企業は全体の17%に過ぎないと指摘している。これは裏を返せば、8割以上の企業が「AIのポテンシャルを十分に活かせていない」ということでもある。
AI導入は、単なる道具の追加ではなく、働き方そのものの設計を見直すこととセットでなければ意味がない。日本企業は今、まさにその転換点に立たされている。
なぜAIで仕事が増えてしまうのか?
表面的には「AIを導入すれば仕事が楽になる」と考えがちだ。しかし現実はその逆で、AIによってかえって仕事が複雑化・増加しているケースが多い。Asanaの調査では、週15時間の情報検索や10時間のツール操作に多くの人が悩まされている。これはまさに“AIパラドックス”の本質だ。
なぜこうなるのか?原因のひとつは、AI導入が「全体設計」ではなく「部分最適」にとどまっていること。たとえば、AIチャットや自動要約といった機能を、既存のフローに追加するだけで導入を完了と見なす企業は少なくない。しかしそれでは、業務全体の流れがかえって煩雑になることもある。
ある企業では、会議の自動議事録AIを導入したが、出力精度が低く、最終的には人が全文を見直して修正する運用になっていた。つまり、AIの導入が「確認という新たな仕事」を生み出してしまったのだ。
また、複数のAIツールが乱立することで、社員は「どのツールを使えばいいのか」「どの情報が正か」が分からなくなり、判断負荷が増す。Asanaの調査でも、38%の労働者が「必要な情報の検索に毎週苦労している」と回答しているのは象徴的だ。
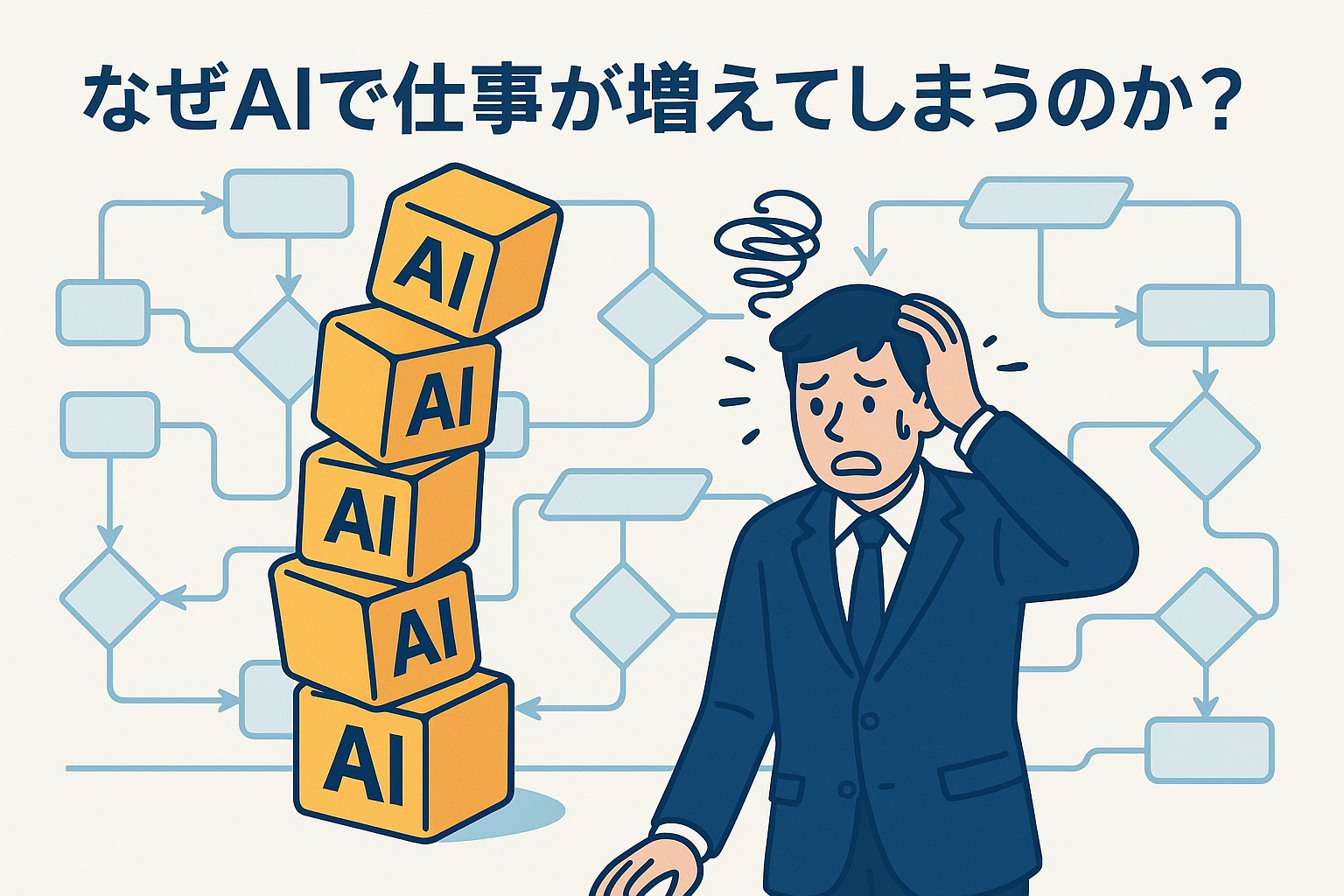
こうした“部分導入の罠”を避けるには、以下のような全体設計が不可欠になる。
- AI導入の目的とKPIを明確化し、現場との合意を形成する
- ワークフロー全体を再設計し、AIとの役割分担を明確にする
AIは万能ではない。人とAI、それぞれの強みを活かす設計をしてこそ、真の業務効率化が実現する。
AIを活かす鍵は「設計」と「対話」
AIが私たちの働き方に入り込み始めた2025年。多くの企業が「生産性向上」を掲げてAIを導入しましたが、その成果は必ずしも期待通りではありませんでした。むしろ、情報検索の手間やツールの使い分けに追われ、「仕事が増えた」と感じる人も少なくないのが現状です。
この“AIパラドックス”の原因は、AI導入が道具の追加で終わってしまい、業務全体の設計や目的の共有が伴っていないことにあります。単なる部分最適ではなく、「なぜ導入するのか」「どこに効果を期待するのか」という問いに正面から向き合うことが、いま企業に求められているのです。
一人ひとりの働き方にとって、AIは“敵”ではなく“相棒”になれる存在です。そのためには、経営層と現場のあいだに対話の橋を架け、AIを業務フローの中に溶け込ませていく工夫が不可欠です。小さな違和感を見逃さず、現場の声に耳を傾けながらAIを育てていく――そんな丁寧なプロセスこそが、AI時代の働き方改革の本質なのかもしれません。
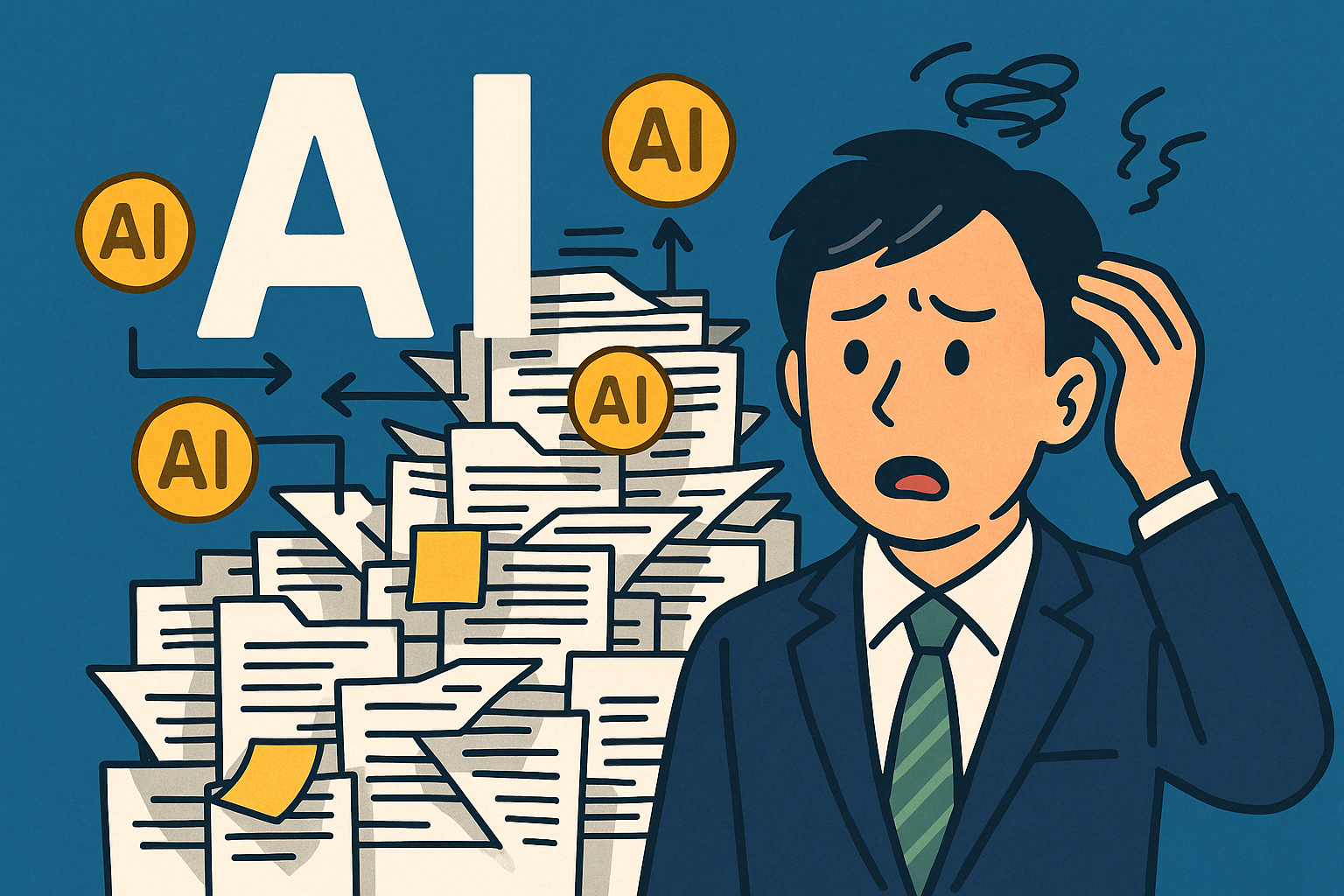


コメント