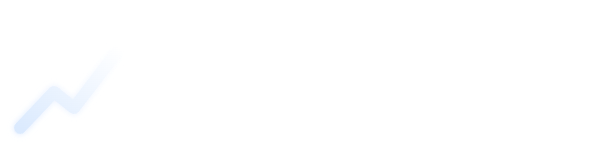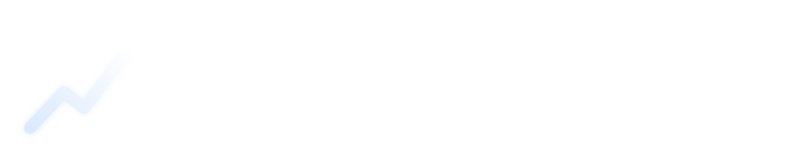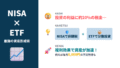399Aって名前は聞くけど、結局どんなETFなのか分かりにくい。
この記事では、399Aの仕組みや特徴を、まず全体から整理していく。
連動している指数やコスト、分配金の考え方。
あわせて、配当貴族型ETF(1494など)との違いにも触れながら、
399Aがどんな投資スタンスの人に向いているかを見ていく。
組入銘柄や業種バランス、分配金や流動性の注意点、
NISAで使う場合の相性まで、ひと通り確認していこう。

なぜ399Aが注目されているのか
高配当ETF(配当を多く出す株に投資する上場投資信託)には似た商品が多い。
ただ、だからこそ399Aの存在感がじわりと効いてくる。
まず、399Aは2025年7月24日に上場したばかりのETFで、日経平均高配当株50指数(配当利回りの高い銘柄を集めた指数)に連動するシンプルな設計だ。
この指数は、日経平均225(日本を代表する225銘柄の株価指数)の中から、配当利回りが高い50銘柄を選んで構成されている。
さらに、信託報酬(保有中にかかる運用コスト)が年0.165%とかなり低い。
そのため、類似する高配当ETFと比べても、コスト面で優位に立ちやすい。
加えて、分配金(ETFから支払われる配当)は年2回(4月・10月)。
売買もしやすく、NISAの成長投資枠(非課税で投資できる制度)でも使いやすい。
一方で、「持続型・高配当」と聞くと、配当貴族(長年配当を出し続けている企業群)のような複雑な仕組みを想像しがちだ。
しかし399Aは、日経平均高配当株50指数に淡々と連動するだけの、素直なETFにすぎない。
それでも、新規ETFとしての期待感と低コストが重なり、結果として注目度が高まっている。
399Aとは?(基本情報)
399Aの基本を整理しておこう。
399Aは、三井住友トラスト・アセットマネジメント(国内大手の資産運用会社)が運用するETFだ。
正式名称は「上場インデックスファンド日経平均高配当株50(上場日経高配当50)」。
投資対象は日経平均高配当株50指数。
この指数では、日経平均225の中から配当利回りが高い50社を選び、毎年6月末に構成銘柄が見直される。
信託期間(運用の期限)は無期限で、東証プライム(東京証券取引所の主要市場)に上場している。
取引は1口から可能。
また、NISAの成長投資枠で購入でき、配当控除(配当と税金を調整する仕組み)の対象にもなる。
運用方針は指数と同じ動きを目指すインデックス運用(指数に連動させる運用)だ。
分配金は、配当などの収益から経費を差し引いたうえで、原則全額を分配する仕組みになっている。
もっとも、将来の分配金が保証されているわけではない。
相場環境によって変わる点は、他のETFと同じだ。
連動指数「S&P/JPX 配当貴族指数」の特徴
比較対象として、S&P/JPX配当貴族指数(配当の安定性を重視した指数)にも触れておきたい。
399Aとよく比べられる「持続型」高配当の代表例だからだ。
この指数は、TOPIX(東証全体を広くカバーする株価指数)構成銘柄の中から、
10年以上、配当を増やすか維持している企業を選ぶ。
さらに、時価総額や流動性(売買のしやすさ)の条件を満たし、配当利回りが高い企業が採用される。
指数は、S&Pダウ・ジョーンズと日本取引所グループが共同で作成し、2006年7月から算出されている。
1銘柄の組入比率は最大5%までに制限され、年1回(7月)にリバランス(銘柄入れ替え)が行われる。
つまり、単なる高配当ではなく、「長く安定して配当を出せるか」を重視した指数だ。
この指数に連動するETFとしては、「One ETF 高配当日本株(1494)」がある。
一方、399Aは直近の予想配当利回りを重視する。
増配の歴史までは考慮しないため、両者は似ているようで性格が異なる。
持続性重視なら配当貴族、
今の利回り重視なら399A、
という整理もできる。
採用銘柄と業種バランス
次に、399Aの組入銘柄を見てみよう。
2025年10月末時点で48銘柄を保有しており、指数の50銘柄とほぼ同じ構成だ。
武田薬品工業、日本郵船、野村HD、アステラス製薬、本田技研、三菱商事、JT、川崎汽船、INPEXなど、
いわゆる「高配当の常連」が中心になっている。
業種別では、
輸送用機器が約10.0%で最も高く、
銀行業(約8.8%)、卸売業(約8.1%)、海運業(約7.4%)、鉄鋼業(約7.3%)が続く。
高配当株指数の特性上、景気敏感株(景気の影響を受けやすい銘柄)が多めだ。
指数が変われば業種の偏りも変わるため、「どんな色合いか」を意識することは大切だ。
基本スペックまとめ
- 上場日:2025年7月24日
- 取引所:東証プライム
- 取引単位:1口
- 信託期間:無期限
- 信託報酬:年0.165%(税込)
- 分配頻度:年2回(4月・10月)
- NISA:成長投資枠で購入可能
こうして整理すると、399Aはやはりコストの軽さが際立つ。
NISAでも使いやすく、人気が高まっている理由が見えてくる。
分配金実績・利回り
399Aは上場したばかりのため、分配実績はまだ1回だけ(2025年12月時点)。
初回(2025年10月4日)の分配金は、1口あたり26円。
基準価額1,707.81円に対して、半年で約1.5%の利回りとなる。
単純に年換算すると、およそ3.0%程度だ。
ただし、この水準が今後も続くとは限らない。
分配金は業績や相場環境に左右されるため、あくまで目安として見ておきたい。
値動きとボラティリティ(事実のみ)
399Aの基準価額は、上場後から10月末にかけて指数とほぼ同じ動きで緩やかに上昇した。
初回分配前後には分配落ちによる一時的な下落があったが、その後は落ち着いて推移している。
上場からの期間が短く、ボラティリティ(価格変動の大きさ)を統計的に評価できるほどのデータはまだない。
構成銘柄は国内大型株が中心のため、一般的には日経平均やTOPIXと同程度の変動性になると考えられる。
ただし、流動性はまだ十分とは言えず、売買高が少ない日は約定しにくい場面もある。
NISAとの相性(一般論)
399Aは新NISAの成長投資枠で購入でき、分配金や売却益が非課税になる。
通常かかる約20%の税金が不要になる点は、大きなメリットだ。
また、国内株のみで構成されているため、為替リスク(円安・円高の影響)がない。
円建てで分配金を受け取りたい人には扱いやすい。
メリット(一般論)
- 高配当株に分散投資できる
- 信託報酬が低い
- 年2回の分配でインカムを得やすい
- NISAで非課税メリットがある
- 国内株中心で分かりやすい
注意点(一般論)
- 上場から間もなく流動性が低め
- 景気敏感な業種が多い
- 実績が短く、長期評価はこれから
どんな投資家と相性が良いか
399Aは、分配金を重視する中長期の投資家と相性が良い。
個別株よりも分散を効かせて、高配当を取り入れたい人向けだ。
一方、短期売買や成長株中心の投資には向かない。
「日本株の高配当を、できるだけ低コストで持ちたい人」に合ったETFといえる。