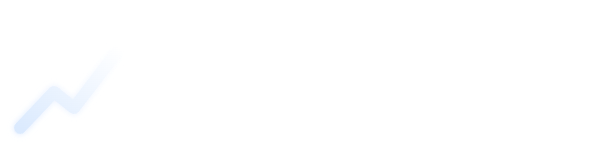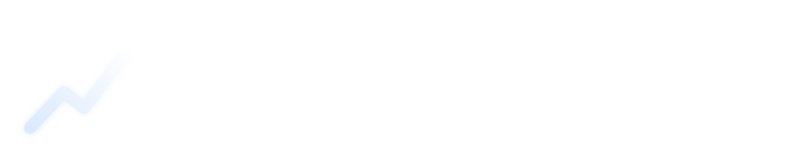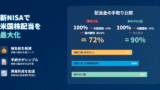高配当ETFで一番ムダなのは、買ってから配当月を知ること。
このページは「配当はいつ」「入金はいつ」「手取りはどれくらい」を早見表で一気に片付ける保存版。
1口・10口・NISA投資の目安額まで並べて、数字が苦手でも流れが頭に入る形にしてある。
まず一覧→次にシミュレーション、で迷いを潰そう。

この記事でわかること
主要な日本の高配当ETFの配当月・回数
1口/10口/NISA投資(目安額)での年間受取額イメージ
税引後ベースで見た“リアルな手取り感”
毎月配当を狙うための ETFの組み合わせ例
すべて 早見表+補足解説 で整理。(数字が苦手でも、配当の流れが頭に浮かぶ構成)

高配当ETFとは?(おさらい)
高配当ETFとは、配当利回りの高い株式で構成された指数に連動するETF(上場投資信託)のこと。
代表例が、
日経平均高配当株50指数
→ 日経平均225の中から、予想配当利回りの高い50銘柄で構成される。
これに連動するETFが 1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50) 。
ほかにも、
- 野村日本株高配当70指数
- MSCIジャパン高配当利回り指数
などをベースにしたETFがある。
高配当ETFの特徴
- 少額で 複数銘柄に分散
- 定期的に 分配金(配当)
- ただし 配当額・回数はETFごとに違う
だからこそ、「配当月の把握」が重要になる。
配当月と配当額の早見表(主要ETF)
※以下は 直近実績ベースの目安
※将来の配当を保証するものではありません
| ETF | 配当頻度 | 配当月 | 1口あたり分配金の目安 |
|---|---|---|---|
| 1489 | 年4回 | 1・4・7・10月 | 数円〜30〜40円程度 |
| 1577 | 年4回 | 1・4・7・10月 | 数十円〜数百円(振れ幅大) |
| 399A | 年2回 | 4・10月 | ※新ETF(実績形成中) |
| 1478 | 年2回 | 2・8月 | 約40〜50円 |
| 2558 | 年2回 | 6・12月 | 年間約250円前後 |
配当月の特徴
- 4月・10月:多くの国内ETFで配当が厚い
- 1月・7月:やや控えめ
- 米国株系(2558):6月・12月
これは、日本企業の多くが 3月決算 である影響が大きい。
1口・10口・NISA投資の受取額シミュレーション
ここでは 年間配当ベースの目安 を整理する。
※利回りは直近実績・想定値
※税引後は課税口座(20.315%)を想定
| ETF | 年利回り目安 | 1口(税前/税後) | 10口(税前/税後) |
|---|---|---|---|
| 1489 | 約3.4% | 約88円/約70円 | 約880円/約700円 |
| 1577 | 約3.1% | 約1,380円/約1,100円 | 約13,800円/約11,000円 |
| 399A | 想定3%台 | 約70円/約56円 | 約700円/約560円 |
| 1478 | 約2.5% | 約104円/約83円 | 約1,040円/約830円 |
| 2558 | 約1.0% | 約256円/約204円 | 約2,560円/約2,040円 |
1口でも意味ある?
正直、金額的なインパクトは小さい。
ただし、
- 配当の流れを体感できる
- 分配月を把握できる
- 継続投資のモチベになる
この意味では、1口は「練習」として悪くない。
NISAを使うと手取りはどう変わる?
配当には通常 20.315%の税金 がかかる。
つまり、利回り3%でも 実質は約2.4% だ。
NISA(少額投資非課税制度)なら?
※NISA=一定枠内の投資が非課税になる制度
- 配当・売却益が 非課税
- 同じ配当でも 約2割多く手元に残る
高配当ETFとNISAは、相性がいい。
これは事実だ。
※新NISAでは
・年間投資枠:成長投資枠 最大360万円
・生涯非課税枠:最大1,800万円
という前提あり(制度は将来変更される可能性あり)
国内ETFと海外ETF|税金の違い(重要)
ここ、地味だけど大事。
国内株ETF(1489・1577など)
- 日本の税金(20.315%)のみ
- NISAなら 完全非課税
海外株を含むETF(2558など)
- 海外で 約10%源泉徴収
※源泉徴収=配当が支払われる前に自動で引かれる税金 - その後、日本で課税(NISAなら国内分は非課税)
→ NISAでも海外税は戻らない
これを知らないと「思ったより少ない」と感じやすい。
毎月配当を目指す組み合わせ例
国内ETFを組み合わせることで、ほぼ毎月入金は可能。
| 月 | ETF |
|---|---|
| 1月 | 1489・1577 |
| 2月 | 1478 |
| 4月 | 1489・1577・399A |
| 6月 | 2558 |
| 7月 | 1489・1577 |
| 8月 | 1478 |
| 10月 | 1489・1577・399A |
| 12月 | 2558 |
※3・5・9・11月は空きやすい
→ 米国ETFやREIT系で補う考え方もある(リスク理解が前提)
注意点(必ず読んでほしい)
減配リスク
配当は 保証されない。
好調だったETFでも、減配・無配は普通に起こる。
価格変動
高配当ETFでも、相場が荒れれば普通に下がる。
「配当があるから安心」は幻想。
セクター偏り
銀行・商社などに偏りやすい。
分散は“万能”じゃない。
コスト
信託報酬(運用コスト)は 静かに効く。
同じ指数なら、基本は低コスト有利。
- 配当月を把握する
- 税引後ベースで考える
- NISAをどう使うかを決める
これだけで、配当投資の見え方はかなり変わる。
高配当ETFは「一発逆転」じゃない。
でも、淡々と積み上がる現金は、思っているより心強い。
焦らず、仕組みを理解して付き合う。
それが、長く続く投資のコツ。